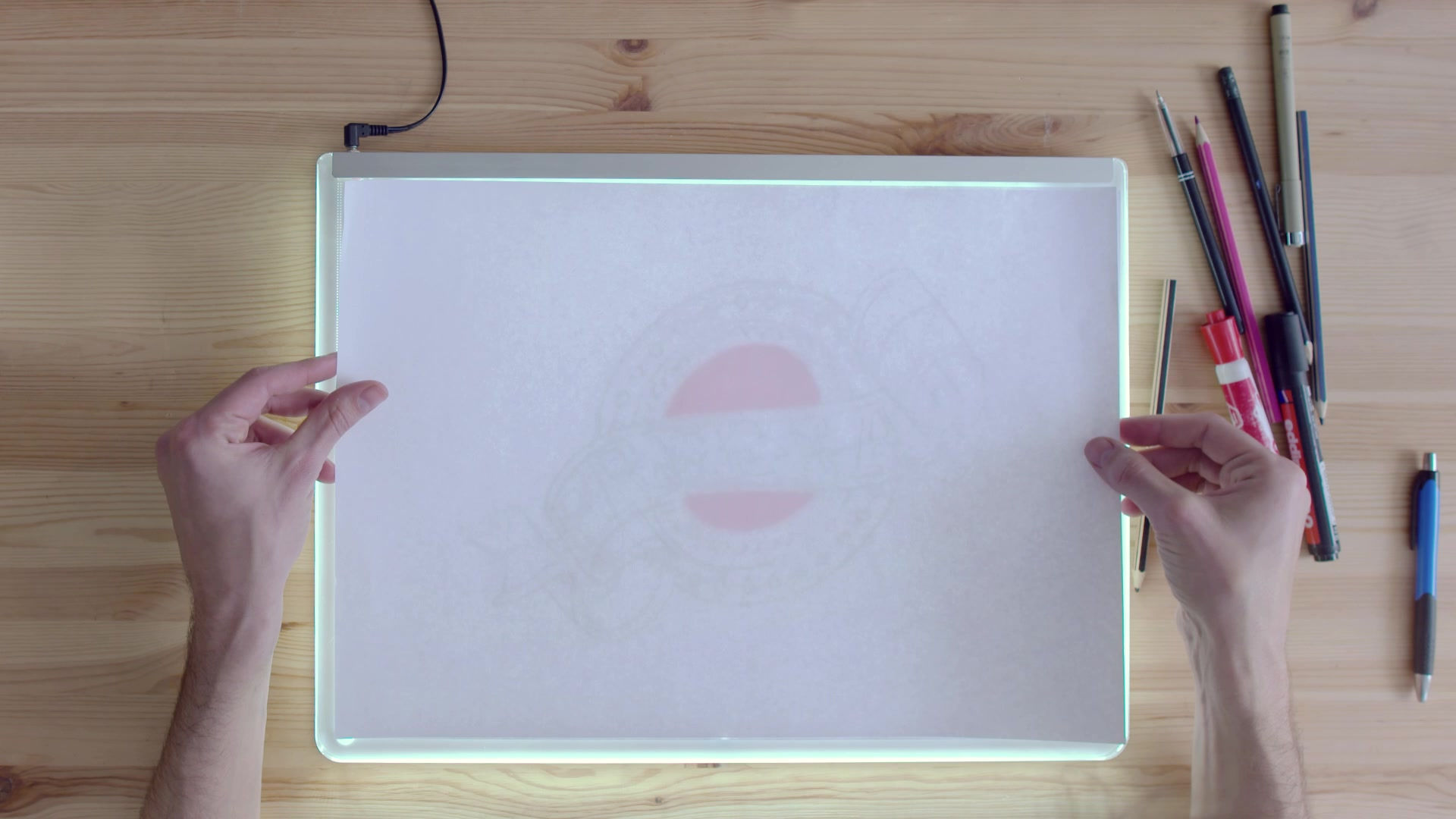
発表者へのご案内
準備中

KUDO Lab
徳島大学
大学院医歯薬学研究部口腔生命科学分野
フォトニクス健康フロンティア研究院/IPHF 実験腫瘍学部門


Research
研究テーマ
1. ユビキチン分解による細胞周期制御機構とその破綻による癌病態の解明(工藤)
2. 口腔癌の浸潤・転移に関わる新規因子の同定とその機能(工藤、毛利、山本)
3. 多能性幹細胞の未分化能維持機構(工藤)
4. 歯原性上皮細胞分化制御機構の解明(工藤)
5. エネルギー代謝関連酵素であるアデニル酸キナーゼ・アイソザイムの機能と生理的意義の解析(堀口)
6. 膵β細胞における細胞機能維持機構の解明と疾患関連性の解析(水澤)
7. 唾液腺細胞株を用いたマイクロRNAの機能解析(水澤)
1. ユビキチン分解による細胞周期制御機構とその破綻による癌病態の解明
ユビキチンープロテアソーム経路によるタンパク分解は、生命活動の場で広範な役割を担っており、タンパク分解におけるユビキチン化の異常は、癌、神経変性疾患などの様々な疾病に関与することが明らかにされつつある。そのため、ユビキチンに関する研究は飛躍的に発展しており、タンパク質にユビキチンを連結させる酵素(ユビキチンリガーゼ)の分子的実体が明確になってきている。 タンパク質のユビキチン化は、ユビキチン活性化酵素(E1)、ユビキチン結合酵素(E2)、ユビキチンリガーゼ(E3)により、ユビキチンがATP依存性に標的タンパクのリジン残基にイソペプチド結合される。このE1-E2-E3のカスケード反応が繰り返されることにより、多数のユビキチンが結合し、ポリユビキチン鎖が形成され、ポリユビキチン化されたタンパクは26Sプロテアソームにより分解される。このユビキチン化機構において、特にE3ユビキチンリガーゼが標的タンパクの認識に重要な役割を果たしており、哺乳類ではE1が3種類、E2が65種類あるのに対して、E3は1000種類を超えると言われている。
一つの細胞が二つの娘細胞を生み出す一連の過程である細胞周期の制御異常は、癌の発生における必須のイベントであることがよく知られている。実際に、これまでに細胞周期調節因子の発現異常に関する多くの研究がなされてきたが、これら異常が生じるメカニズムの多くが未だ明らかにされていない。細胞周期調節因子の多くがユビキチン化を介したタンパク分解により厳密にそのタンパク量が調節され、細胞周期の円滑な進行を制御することが明らかにされつつあるが、この制御機構の異常と癌化との関連は未だに明らかにされていないことが多い。細胞周期制御に関わるユビキチンリガーゼとして、SCF(Skp1-Cullin-F-box)複合体およびAPC/C(anaphase promotingcomplex/cyclosome)複合体が知られている。SCFは、Skp1, Cul1, F-boxタンパク、Roc1が複合体を形成して働き、なかでもF-Boxタンパクは、哺乳類では69種類が存在し、標的タンパクへの基質特異性を決定している。APC/Cユビキチンリガーゼは、11個のサブユニットからなる大きな複合体で、時期特異的なユビキチン化に関わるアダプター因子であるCdc20やCdh1の可逆的な結合や構成サブユニットのリン酸化によってその活性が調節されている。APC/C-Cdc20は、分裂前期から前中期にかけて活性化し、分裂後期から終期になるとAPC/C-Cdh1が活性化する。APC/C-Cdh1の活性はG1/S期の移行期まで続き、その後は、APC/C inhibitorであるEmi1によりその活性が阻害される。APC/C-Cdc20は、M期の紡錘体チェックポイント制御に中心的な働きをし、APC/C-Cdh1は、細胞分裂を司る多くの因子をG1期で分解することが知られている。これまで、SCF複合体及びAPC/C複合体による細胞周期調節因子のユビキチン分解制御機構やその異常による癌化に着目して、以下のような研究を行ってきた。
-
体細胞における細胞周期制御とその異常(下図参照)
1) SCFßTrcp1によるEmi1のユビキチン分解
Pagano研究室に留学中に、F-boxタンパクの1つであるß-Trcp1(FBXW1A)に着目して研究を行った。当時、ß-Trcp1は、I𝜅B𝛼やß-cateninのユビキチン分解に関わることが知られていた。ß-Trcp1ノックアウト(KO)マウスを作製し、そのphenotypeを解析したところ、特に異常はみられなかった。これは、ß-Trcp1のホモログであるß-Trcp2(FBXW11)によるI𝜅B𝛼やß-cateninの分解制御が正常であることによると考えられる。唯一のphenotypeとして、ß-Trcp1 KOマウス雄に不妊傾向があり、精祖細胞の分裂異常により精子形成が阻害されていることを見出した。その詳細な解析から、細胞分裂制御に関わるEmi1(FBXO5)を新規基質タンパクとして同定した(Dev Cell 4:799-812, 2003)。Emi1は、APC/Cユビキチンリガーゼの活性を抑制する因子として知られており、M期初期にSCF-ß-TrcpによるEmi1のユビキチン分解により、APC/Cが活性化することを明らかにした。
2) APC/C-Cdh1によるAurora-Aタンパク質のユビキチン分解機構
Aurora-Aは、分裂期チェックポイント因子として時間的・空間的にダイナミックに動きながら様々な基質タンパク質をリン酸化し、M期への進行、中心体の分離、紡錘体の形成、染色体の分離や細胞質分裂などを調節している。Aurora-Aタンパクは、S期からM期まで発現し、G1期にAPC/C-Cdh1ユビキチンリガーゼによりユビキチン分解される。申請者らは、ヒトAurora-Aタンパク質がAPC/C-Cdh1によりユビキチン分解されることを初めて報告した(PLoS ONE 2:e944, 2007)。また、M期においてAurora-Aタンパクの51番目のセリン残基(Ser51)がリン酸化されることで、APC/C-Cdh1によるユビキチン分解から免れ、安定化することを明らかにした。
3) M期におけるAPC/C-Cdh1によるGemininのユビキチン分解制御機構
APC/C-Cdh1の基質タンパク質として知られるGemininは、1細胞周期においてDNA複製を1回に規定する。Gemininは、S-G2期において複製前複合体(pre-replication complex; pre-RC)の形成に必須なCDT1に直接結合し、そのゲノムへの結合を阻害することで、再複製を抑制する。その後、GemininはG1期にAPC/C-Cdh1によりユビキチン分解される。よって、APC/C活性の高いM期終期からG1期にかけてのみpre-RC形成は起こる。これまでに、Gemininタンパク質のM期での存在意義はよくわかっていなかった。申請者らは、Gemininが、M期においてAurora-AによりThr25がリン酸化されることにより,APC/C-Cdh1による分解から免れ,安定化することを見出した。さらに、安定化したGemininは、SCFSkp2を介したCDT1のユビキチン分解を抑制し、CDT1を安定化させることで、M期終期からG1期におけるpre-RC形成を適切に誘導し、次のS期でのDNA複製を保証することを明らかにした(Nat Commun 4:1885, 2013)。
4) APC/C-Cdh1によるBorealinのユビキチン分解制御機構
染色体パッセンジャー複合体は、活性の中心となるAurora-Bキナーゼ、その活性を制御すると考えられているSurvivinやBorealin、複合体の足場として働くINCENPの4つのタンパク質より構成されている。染色体パッセンジャー複合体は、Aurora-Bによる様々な基質タンパク質のリン酸化を介して、正確な染色体分配を制御するキー調節因子として機能する。申請者らは、Borealinタンパク質が、G1期においてAPC/C-Cdh1によりユビキチン分解され、それにより染色体パッセンジャー複合体の機能が終わることを見出した。APC/C-Cdh1は、通常RxxLやKENという分解配列を認識してユビキチン分解するが、Borealinはcanonicalな分解配列ではなく、特異的な配列により認識されていることを明らかにした(J Cell Sci 133(18):jcs251314, 2020)。
5) Cyclin FによるRRM2のユビキチン分解によるDNA修復機構(Pagano教授との共同研究)
DNAの複製と修復に必要なリボヌクレオチドのdNTPへの変換を触媒するリボヌクレオチドリダクターゼであるRRM2が、G2期においてCyclin F(FBXO1)によりユビキチン分解され、dNTP量とゲノム安定性の維持に関わることを明らかにした(Cell 149:1023-1034, 2012)。さらに、DNA損傷時にはCyclin Fの発現低下によりRRM2タンパクが安定化することにより、dNTP量を調節し、効率的なDNA修復をもたらすことを明らかにした。
6) SCF-ßTrcpによるCDC25Bのユビキチン分解によるストレス応答機構(金沢大学 山下准教授との共同研究)
MAPキナーゼ経路を活性化する細胞ストレスが、細胞周期のG2-M期への進行に関わるフォスファターゼであるCDC25Bをリン酸化して、SCFßTrcpによりユビキチン分解され、G2期停止を引き起こすことを見出した(J Cell Sci 124:2816-2825, 2011)。
7) 癌におけるSCF-Skp2によるp27Kip1の分解 癌におけるp27Kip1の発現低下には、過剰なユビキチン分解が関与することが明らかになり、プロテアソーム阻害剤の投与によるp27Kip1の分解抑制や非分解型p27Kip1の遺伝子導入は,癌細胞にアポトーシスを誘導することを明らかにした(Clin Cancer Res 6:916-923, 2000; Oncology 63:398-404, 2002)。p27Kip1タンパクがG1期からS期へ進行する際に、F-boxタンパクであるSkp2(FBXL1)によりユビキチン化され、Skp2のp27Kip1への結合にアクセサリータンパクであるCks1が必要であることが報告され(Nat Cell Biol 1: 193-199, 1999; Nat Cell Biol 3: 321-324, 2001)、申請者らは口腔癌症例及び培養細胞株において,Skp2やCks1が高頻度に過剰発現し、p27Kip1の発現低下や予後と相関することを見出した(Cancer Res 61:7044-7077, 2001; Am J Pathol 165:2147-2155, 2004)。また、癌細胞におけるsiRNAによるSkp2のノックダウンは、p27Kip1の分解抑制を介して増殖を抑制することを明らかにした(Mol Cancer Ther 4:471-476, 2005)。
8) 乳癌におけるSCF-ßTrcp1による発癌機構
ß-Trcp1は乳癌症例において、過剰発現が高頻度に認められることから、乳腺特異的に発現するMMTVプロモーターを用いてß-Trcp1トランスジェニック(TG)マウスを作製した。ß-Trcp1 TGマウスは、I𝜅B𝛼のユビキチン分解を介した恒常的なNF-𝜅Bの活性化を介して、乳腺の導管形成を促進し、乳癌を発症することを見出した(Mol Cell Biol 24:8184-8194, 2004)。
9) Aurora-Aタンパク質のユビキチン分解異常による癌化機構
ヒトAurora-A遺伝子AURKA/STK15は、20q13.2に位置し、多くの癌で遺伝子増幅とmRNAの過剰発現が報告されている。Aurora-Aキナーゼ阻害剤は、新規抗がん剤として臨床応用されつつある。申請者らは、癌におけるAurora-Aタンパクの過剰発現が、従来その原因と考えられていた遺伝子増幅やmRNAの過剰発現では説明できないことを見出した(PLoS ONE 2:e944, 2007; Mol Carcinog 48:810-20, 2009; Front Oncol 5:187, 2015)。Aurora-AのSer51の恒常的なリン酸化を示す癌細胞では、遺伝子増幅やmRNAの過剰発現を示す癌細胞に比べて、ユビキチン分解阻害により強力に過剰発現が引き起こされることを見出し、新たなAurora-Aの過剰発現機構を提唱した。
10) Emi1のknockdownによる再複製の誘導と癌治療への応用
APC/Cの活性を阻害するEmi1のknockdownは、APC/Cの活性化によるGemininタンパクの分解により、DNAの再複製による増殖停止を引き起こす(Genes Dev 21:184-194, 2007; J Cell Biol 177:425-437, 2007)。我々は、Emi1が口腔癌を含めた多くの癌で過剰発現していることを見出し、種々の癌細胞において、Emi1 siRNAによる発現低下がAPC/C-Cdh1の活性化によるDNA再複製を引き起こし、増殖をさせることを見出した( J Biol Chem 288:17238-17252, 2013)。さらに、Emi1のknockdownが、DNA複製を標的にした抗癌剤や放射線照射の抗癌効果を増強させることを明らかにした。
-
多能性幹細胞におけるユビキチン分解制御(下図参照)
1) SCF-Fbxo15によるミトコンドリア生合成調節機構(ニューヨーク大学 Pagano教授との共同研究)
マウスES細胞において、ミトコンドリア関連キネシンKif1Bαの結合因子であるKBPタンパクが、アセチル化を介してFbxo15によりユビキチン分解されることを見出した(Nat Cell Biol 19:341-351, 2017)。マウスES細胞では、KBPタンパクはユビキチン分解され、ミトコンドリアの蓄積を制限して最適な適応性を維持するが、分化細胞ではKBPは分解を受けずに蓄積し、ミトコンドリアの生合成を促進することを明らかにした。
2) BorealinによるAurora-Bキナーゼ活性を介した未分化能維持機構
胚性幹細胞において、細胞周期を通じてEmi1が安定化することにより、APC/Cの活性が低く調節されていることが報告された(PNAS 108:19252-7, 2011; Nat Commun 7:10660, 2016)。申請者らは細胞分裂に重要な役割を果たす染色体パッセンジャー複合体の構成因子の1つであるBorealinタンパクが、体細胞においてAPC/C-Cdh1によりユビキチン分解されることを見出した。胚性幹細胞では、Borealinタンパクは細胞周期を通じて安定化しており、レチノイン酸投与による分化過程で、APC/C-Cdh1によりユビキチン分解されることを見出した。さらに、胚性幹細胞におけるBorealinのknockdownは、未分化マーカーの発現減少と分化マーカーの発現亢進を誘導し、この現象はAurora-Bのキナーゼ活性低下によるものであることを明らかにした。実際に、Aurora-Bキナーゼ阻害剤の投与でも同様の現象を確認した。このように、多能性幹細胞においてBorealinは、Aurora-Bのキナーゼ活性を介して未分化能維持に重要な役割を果たすことを見出した(Sci Signal 18: Issue 874, 2025)。現在、多能性幹細胞の維持に関わるAPC/C-Cdh1の基質タンパク質を探している。
2. 口腔癌の浸潤・転移に関わる新規因子の同定とその機能
近年、口腔癌の発生率は増加傾向にあり、世界では5番目に高い頻度の癌である。現在の一般的な治療法として、外科的切除が行なわれるが、審美的・機能的、あるいは心理的な損失が大きく、QOLの低下が著しい。そこで、外科的切除に頼らない治療法として、すでに応用されつつある免疫療法、超選択的動注化学療法やなどに加えて、癌の発生進展に関わる遺伝子を標的としたより特異的な治療の開発が求められている。そのためには、癌の発生や進展に関する分子メカニズムの解明が必要となる。通常、粘膜表層に生じた口腔癌細胞は、深部へ浸潤し、頚部リンパ節や他臓器へと転移していく。深部への浸潤や転移の有無は、患者の予後を左右する最も重要な因子であることから、浸潤・転移機構の解明は、癌の制御においてとりわけ重要な課題である。我々は、口腔癌の浸潤・転移機構を明らかにし、その悪性度診断ならびに遺伝子治療への応用を目的に研究に取り組んできた。
我々は、これまでに、口腔患者の頚部リンパ節転移巣より、高浸潤能を有する細胞株を樹立し(Oral Oncol, 2003)、その細胞よりin vitro invasion assay法を応用して分離した高浸潤能を有するクローンが、E-cadherinのメチル化および細胞膜に存在するß-cateninが分解されることにより高浸潤能を獲得していることを報告した(Clin Cancer Res, 2004)。さらに、我々は、マイクロアレイを用いて、親株と高浸潤能細胞の遺伝子発現プロファイルを比較することにより、浸潤に関わる候補遺伝子をいくつか同定した(下図参照)。
候補遺伝子のうち最も差のみられたPeriostinは、in vitroおよびin vivoで口腔癌の浸潤・転移に深く関わるとともに、in vivoで広範な浸潤による転移を引き起こすことを証明し、癌に特異的なスプライシングバリアントを同定した(Cancer Med 12:8510-8525, 2023; Cancer Res, 2006; Br J Cancer, 2006)。さらに、2番目に発現に差のみられた因子であるInterferon induced transmembrane protein 1 (IFITM1)も口腔癌の初期浸潤に関わることを明らかにした(Clin Cancer Res, 2008)。そのほか、Wnt5B,MMP-10,MMP-13なども口腔癌の浸潤に関わる新規因子として同定し,これら因子の浸潤への関与をin vitroで詳細に解析するとともに,口腔癌の手術材料やパラフィン包埋切片を用いて臨床病理学的意義を明らかにした(PLoS ONE, 2011; PLoS ONE, 2012; J Biol Chem, 2012; Oncotarget, 2016)。我々が同定した口腔癌の浸潤に関わる新規因子の中には,他の悪性腫瘍の浸潤・転移やEMT(上皮間葉移行)に関与するものもあり,現在までに多くの我々の研究成果をサポートする論文が報告されている。
また、口腔癌の進展には、完全なEMTより部分的なEMT(Partial-EMT)がより悪性度に関わることを示した(Sci Rep 14:6767, 2024; Cancer Med 12:8510-8525, 2023; J Oral Biosci, 64:176-182, 2022; Sci Rep 1:14943, 2021; Int J Mol Sci 21:6207, 2020; Oral Dis 26: 1149-1156, 2020)。特に,Partial-EMTは癌の悪性度に関わる因子の中で最も重要であると考えられ,着目されている.これら因子は,癌の予後を予測する有用なマーカーのみならず,新たな治療標的になることが期待される.最近では公開データベースにある臨床情報を有するHNSCC症例の遺伝子発現データを活用した研究に取り組んでいる。



